車 エンジン 回転数 不安定の徹底解説の完全ガイド

車の運転中、あるいはアイドリング中に、エンジンの回転数が不規則に上下したり、安定しないと感じたことはありませんか?これは「エンジン回転数不安定」と呼ばれる症状で、多くのドライバーが経験する可能性のある不具合の一つです。単なる一時的な現象として見過ごされがちですが、実は車の様々な重要なシステムに起因する可能性があり、放置すると燃費の悪化、排ガスの増加、最悪の場合、エンジンへの深刻なダメージや走行中のエンストに繋がることもあります。
この記事では、車のエンジン回転数が不安定になる原因から、その種類、自分でできる初期診断、具体的な対処法、さらには予防策や費用まで、徹底的に詳しく解説します。あなたの愛車が快適で安全な状態を保つために、この完全ガイドをぜひお役立てください。
1. 車 エンジン 回転数 不安定の徹底解説の基本

エンジンの回転数が不安定になるという症状は、車の心臓部であるエンジンが正常に機能していないサインです。具体的には、アイドリング時にタコメーターの針が一定の範囲内で不規則に変動したり、走行中にアクセルを踏み込んでいるにも関わらずエンジンのパワーが安定しなかったり、あるいは停車時にエンストしそうになるなどの現象を指します。この不安定さは、エンジンの燃焼プロセスを構成する「良い混合気(燃料と空気のバランス)」「良い圧縮(シリンダー内の圧力)」「良い火花(点火)」のいずれか、または複数の要素が適切に機能していないことを示唆しています。
エンジンの回転数が不安定になる主なメカニズムは、燃料供給の異常、吸気系統の問題、点火系統の不具合、排気系統の詰まり、センサーの故障、あるいはエンジンを制御するECU(エンジンコントロールユニット)の異常など、多岐にわたります。これらの要素は互いに密接に関連しており、一つが不調を来すと全体のバランスが崩れ、結果として回転数の不安定さに繋がるのです。例えば、燃料噴射が不規則になったり、吸入空気量が正確に測定されなかったりすると、エンジンが必要とする適切な混合気が供給されず、燃焼効率が低下します。また、点火プラグの劣化やイグニッションコイルの不具合は、適切なタイミングでの火花供給を妨げ、これもまた不完全燃焼の原因となります。
⚠️ この症状を放置することは、単なる不快感に留まらず、燃費の著しい悪化、排ガスの増加による環境負荷の増大、そして最終的にはエンジンの寿命を縮めることに繋がります。特に、走行中に急なエンストが発生する可能性もあり、重大な事故を引き起こすリスクもゼロではありません。そのため、エンジン回転数の不安定さを感じたら、早期に原因を特定し、適切な対処を行うことが極めて重要です。自分でできる簡単なチェックもありますが、原因の特定や修理には専門的な知識と技術が必要となる場合がほとんどであるため、信頼できる整備工場への相談をためらわないでください。
2. 車 エンジン 回転数 不安定の徹底解説の種類

エンジン回転数の不安定さには、いくつかの異なる種類があり、それぞれが異なる原因を示唆している場合があります。症状の種類を理解することは、トラブルシューティングの第一歩となります。💡 これらの症状と原因の関連性を把握することが、的確な診断と修理への重要なポイントです。
- アイドリング時のハンチング(回転数の上下動):
- 症状: 停車時や信号待ちなどでアクセルを踏んでいない状態(アイドリング時)に、タコメーターの針が一定の範囲で上下に不規則に動く現象です。
- 主な原因:
- 吸気系統の異常: エアフロセンサー(吸入空気量センサー)の汚れや故障、スロットルボディの汚れ、ISCバルブ(アイドルスピードコントロールバルブ)の不具合、バキュームホースの亀裂や抜けによる二次空気の吸い込み。
- 点火系統の異常: 点火プラグの劣化、イグニッションコイルの故障。
- 燃料系統の異常: 燃料フィルターの詰まり、燃料ポンプの不調、インジェクターの汚れや詰まり。
- センサーの異常: O2センサーの故障、クランク角センサーの不調。
- 走行中の息つき・もたつき(加速時の不調):
- 症状: アクセルを踏み込んだ際に、エンジンがスムーズに加速せず、一瞬息を吸い込むような、あるいは引っかかるような感覚が生じる現象です。
- 主な原因:
- 燃料供給の不足: 燃料フィルターの詰まり、燃料ポンプの性能低下、インジェクターの汚れ。
- 点火不良: 点火プラグの劣化、イグニッションコイルの故障。
- 吸気系統の詰まり: エアフィルターの詰まり。
- ターボチャージャーの不調: ターボ車の場合、ターボチャージャーの故障。
- エンスト寸前・エンスト(停止時の不調):
- 症状: 停車時や低速走行時にエンジンの回転数が極端に低下し、ガタガタと振動してエンストしそうになったり、実際にエンストしてしまう現象です。
- 主な原因:
- ISCバルブの固着や故障: アイドリング時の空気量を適切に調整できないため。
- スロットルボディの汚れ: アイドリング時の空気通路が狭くなるため。
- 燃料ポンプの不調: 燃料供給が不安定になるため。
- バッテリーの劣化やオルタネーターの不調: 電圧が不安定になり、エンジン制御に悪影響を及ぼすため。
- 特定の回転域での不調(特定の速度やギアでの問題):
- 症状: 特定のエンジン回転数や車速になったときにだけ、エンジンの振動が大きくなったり、パワーが落ちたりする現象です。
- 主な原因:
- 点火系統の特定のシリンダーでの不良: 特定のプラグやコイルの不具合。
- インジェクターの特定のシリンダーでの不良: 特定のインジェクターの詰まりや故障。
- エンジンマウントの劣化: 振動吸収能力が低下し、特定の回転域で共振する。
これらの症状は単独で発生することもあれば、複数同時に現れることもあります。それぞれの症状が示す可能性のある原因を理解することで、より効率的にトラブルシューティングを進めることができます。しかし、最終的な診断と修理は専門知識と専用ツールが必要となるため、症状を正確に伝え、プロの整備士に依頼することが最も確実な解決策となります。
3. 車 エンジン 回転数 不安定の徹底解説の始め方

エンジン回転数が不安定になる症状に気づいたら、まずは落ち着いて状況を把握し、いくつかの初期チェックを行うことから始めましょう。これは、専門の整備工場に依頼する際にも、症状を正確に伝えるための重要な情報となります。
- 症状の記録と観察:
- いつ発生するか: アイドリング時、走行中(低速、高速)、加速時、減速時、エンジンが冷えている時、温まっている時など、具体的な状況を記録します。
- どのような症状か: 回転数の上下動(ハンチング)、息つき、エンスト寸前、特定の回転域での不調など、具体的に記述します。
- 他の異常はないか: 異音(キュルキュル、カタカタなど)、異臭(焦げ臭い、ガソリン臭い)、排気ガスの色(白煙、黒煙)、警告灯の点灯(特にエンジンチェックランプ)など、付随する症状も確認します。
- 最近のメンテナンス履歴: オイル交換、プラグ交換、エアフィルター交換など、最近行ったメンテナンス作業があれば記録しておきます。
- ボンネットを開けての簡易目視チェック:
- バッテリー端子: 端子が緩んでいないか、腐食していないかを確認します。緩みや腐食は電気系統の不調を引き起こす可能性があります。
- エアフィルター: エアクリーナーボックスを開け、エアフィルターが極端に汚れていないか確認します。詰まっている場合は、吸入空気量が不足し、エンジンの不調に繋がります。
- 各種ホース類: エンジンルーム内のゴムホース(特にバキュームホース)に亀裂が入っていないか、抜け落ちていないかを確認します。二次空気の吸い込みは、回転数不安定の一般的な原因です。
- 点火プラグコード(一部車種): プラグコードがある場合、外れていたり損傷していないか確認します。
- オイル量・冷却水量: これらの量が適正範囲内にあるかを確認します。直接的な原因でなくとも、エンジンの健康状態を示す指標となります。
- 運転感覚の確認:
- アクセルレスポンス: アクセルを踏んだ時のエンジンの反応はどうか。スムーズか、遅延があるか。
- 振動: エンジンからの不自然な振動がないか。
- 燃費の変化: 最近、燃費が悪化していないか。
📌 これらの初期チェックは、あくまで症状の把握と簡単な目視確認に留めることが重要です。専門知識がない状態で無理に分解したり、部品をいじったりすることは、かえって状況を悪化させたり、危険を伴う可能性があります。特に、エンジンが熱い状態での作業や、高電圧がかかる可能性のある部品への接触は避けてください。安全を最優先に考え、少しでも不安を感じたら、すぐに専門の整備工場に相談することが賢明です。この初期段階で得られた情報は、整備士が原因を特定する上で非常に役立つでしょう。
4. 車 エンジン 回転数 不安定の徹底解説の実践

エンジン回転数の不安定さを改善するための実践的なアプローチは、原因によって大きく異なります。自分でできる簡易的なメンテナンスから、専門の整備工場に依頼すべき修理まで、具体的な実践方法を解説します。
- 自分でできる簡易メンテナンス(軽度な症状の場合):
- エアフィルターの清掃・交換: エアフィルターが汚れていると吸入空気量が不足し、不完全燃焼の原因になります。フィルターの状態を確認し、汚れがひどければ交換、軽度であればエアブローなどで清掃します。これは比較的簡単で、DIYでも挑戦しやすい作業です。
- 燃料添加剤の使用: 燃料系統の汚れ(インジェクターや燃焼室のカーボン蓄積)が原因の場合、市販の燃料添加剤(インジェクタークリーナーなど)を使用することで改善されることがあります。ただし、これはあくまで一時的な対策であり、根本的な解決にはならない場合もあります。使用方法をよく守りましょう。
- バッテリー端子の清掃・締め付け: バッテリー端子の腐食や緩みは、電気系統の不安定さを引き起こすことがあります。ブラシで腐食を取り除き、しっかりと締め付けます。作業の際は、ショート防止のため必ずマイナス端子から外しましょう。
- 専門業者に依頼すべき修理(症状が改善しない、または深刻な場合):
- 診断機によるチェック: 整備工場では、OBD-II診断機を車に接続し、ECUに記録されたエラーコードを読み取ります。これにより、どのセンサーやシステムに異常があるかを特定し、原因を絞り込むことができます。これが最も確実な診断方法です。
- スロットルボディの清掃・調整: スロットルボディ内部にカーボンが堆積すると、アイドリング時の空気量が不安定になります。専門業者による清掃や、必要であれば調整・交換が必要です。
- ISCバルブの交換: アイドリング時の空気量を制御するISCバルブが故障している場合、交換が必要です。
- センサー類の交換: エアフロセンサー、O2センサー、クランク角センサーなど、各種センサーの故障が原因の場合、新品への交換が必要です。これらのセンサーはエンジンの燃焼制御に不可欠なため、正確な部品を選ぶ必要があります。
- 点火系統の部品交換: 点火プラグ、イグニッションコイル、プラグコード(一部車種)の劣化や故障が原因の場合、これらを交換します。特に点火プラグは消耗品であり、定期的な交換が推奨されます。
- 燃料系統の修理: 燃料ポンプの故障、燃料フィルターの詰まり、インジェクターの詰まりや故障が原因の場合、それぞれの部品の交換や清掃が行われます。インジェクターの清掃は専門的な設備が必要です。
- バキュームホースの交換: 亀裂が入ったり硬化したバキュームホースは、二次空気の吸い込みを引き起こします。劣化したホースは全て交換するのが望ましいです。
- ECUの診断・修理・交換: 最も深刻なケースでは、エンジンを制御するECU自体に不具合がある場合があります。ECUの修理や交換は高額になることが多く、専門的な知識と技術が必須です。
これらの実践は、原因を特定した上で行う必要があります。自己判断で部品交換を行うと、無駄な出費になったり、かえって別の不具合を引き起こしたりするリスクがあります。症状が改善しない場合や、原因が特定できない場合は、迷わずプロの整備士に相談し、適切な診断と修理を依頼することが、車の安全と寿命を守る上で最も重要な実践です。
5. 車 エンジン 回転数 不安定の徹底解説の注意点
エンジン回転数の不安定さは、車の健康状態を示す重要なサインであり、対処を誤るとさらなる問題を引き起こす可能性があります。ここでは、特に注意すべき点をいくつか解説します。
- 症状の放置は厳禁:
エンジン回転数の不安定さを放置することは、絶対に避けるべきです。
- 燃費の悪化: 不完全燃焼や制御の乱れにより、燃料が無駄に消費され、燃費が著しく悪化します。
- 排ガス悪化: 不完全燃焼は、有害な排気ガス成分の増加に繋がり、環境基準を満たさなくなる可能性があります。
- エンジンへの負担増大: エンジンが常に不適切な状態で稼働することで、各部品への負担が増加し、最終的にはエンジンの寿命を縮めることになります。
- 走行不能・事故のリスク: 最悪の場合、走行中にエンストしたり、加速不良により危険な状況に陥ったりする可能性があります。特に高速道路などでのエンストは、重大な事故に直結しかねません。
- 安易なDIY修理の危険性:
一部の簡単なメンテナンス(エアフィルター交換など)はDIYでも可能ですが、エンジン回転数の不安定さの原因特定や修理は、専門的な知識と経験、専用の工具を必要とします。
- 誤診断のリスク: 原因を間違って判断し、無関係な部品を交換してしまうと、時間と費用が無駄になるだけでなく、本当の原因を見逃して症状が悪化する可能性があります。
- 部品の破損: 不適切な工具の使用や無理な作業は、部品を破損させたり、他の箇所にダメージを与えたりする原因となります。
- 電気系統のショート: バッテリー端子などを誤って扱うと、ショートさせてしまい、ECUなどの高価な電子部品を損傷させるリスクがあります。
- 安全性の問題: エンジンルーム内には高温になる部品や回転する部品、高電圧がかかる部品などがあり、無闇に触れると火傷や感電などの危険があります。
- 信頼できる整備工場の選び方:
専門業者に依頼する際は、信頼できる工場を選ぶことが重要です。
- 診断能力: 経験豊富な整備士が在籍し、OBD-II診断機などの専門ツールを使って正確な診断ができるか。
- 説明の透明性: 診断結果や修理内容、費用について、素人にも分かりやすく丁寧に説明してくれるか。
- 見積もりの明瞭さ: 見積もりが明確で、内訳がきちんと示されているか。不必要な修理を勧めていないか。
- 実績と評判: 口コミやレビュー、整備工場の認証などを参考に、実績のある工場を選びましょう。
これらの注意点を踏まえ、エンジン回転数の不安定さに直面した際は、自己判断に頼りすぎず、安全を最優先に考えてプロの診断と修理を依頼することが、最も賢明な選択と言えます。
6. 車 エンジン 回転数 不安定の徹底解説のコツ
エンジン回転数の不安定さを未然に防ぎ、あるいは早期に発見して適切に対処するための「コツ」をいくつかご紹介します。これらの習慣を身につけることで、愛車の健康を長く保つことができます。
- 定期的なメンテナンスの徹底:
- 消耗品の交換: 点火プラグ、エアフィルター、燃料フィルター、エンジンオイル、オイルフィルターなどは、メーカーが推奨する時期や走行距離に応じて定期的に交換しましょう。これらはエンジンの燃焼効率に直結する部品であり、劣化は回転数不安定の直接的な原因となります。
- プロによる定期点検: 車検時だけでなく、1年点検などのプロによる定期点検を必ず受けましょう。専門家は、診断機を用いたチェックや目視では見つけにくい不具合を早期に発見してくれます。
- 異常の早期発見のコツ:
- 五感を研ぎ澄ます:
- 音: エンジンからの異音(以前はなかった音、特定の回転数で発生する音)に注意を払う。
- 振動: アイドリング時や走行中に、以前とは異なる不自然な振動がないかを感じ取る。
- 臭い: 焦げ臭い、ガソリン臭い、甘い(冷却水)など、普段と違う臭いがしないか確認する。
- 視覚: 排気ガスの色(白煙、黒煙、青煙)や、エンジンルーム内からの煙、オイル漏れなどに注意する。
- 警告灯の確認: エンジンチェックランプやバッテリー警告灯など、警告灯が点灯したらすぐに専門業者に相談しましょう。点灯は、システムに何らかの異常が発生している明確なサインです。
- 燃費の変化: 普段より燃費が著しく悪化している場合、エンジンの燃焼効率が低下している可能性があります。
- タコメーターの観察: アイドリング時や走行中に、タコメーターの針が不自然に上下していないかを意識的に確認する習慣をつけましょう。
- 運転習慣の見直し:
- 急発進・急停止を避ける: エンジンや駆動系に過度な負担をかける運転は、部品の劣化を早めます。スムーズな運転を心がけましょう。
- 適切な暖機運転: エンジンが冷えている状態での高負荷運転は避けるべきです。特に冬場は、発進前に数分間アイドリングさせるなど、適切な暖機運転を心がけましょう。
- 短距離走行の頻度を減らす: 短距離走行が多いと、エンジンが十分に温まらず、カーボンが蓄積しやすくなります。たまには長距離を走行して、エンジンを「焼ききる」ことも有効です。
📌 これらの「コツ」は、日々の車の状態に意識を向けることで、小さな変化にも気づきやすくなり、問題が大きくなる前に対応できる可能性を高めます。特に、五感を使ったチェックは、診断機では捉えきれない「違和感」を早期に発見する上で非常に重要です。愛車と長く付き合うためには、日頃からの細やかな気配りが欠かせません。
7. 車 エンジン 回転数 不安定の徹底解説の応用アイデア
エンジン回転数の不安定さへの対処は、単なる修理に留まらず、車の健康管理全体を向上させるための応用アイデアへと繋がります。ここでは、より積極的な車の維持管理について解説します。
- 車両健康管理アプリ・OBDスキャナーの活用:
- OBD-IIスキャナー: 市販されているOBD-IIスキャナー(Bluetooth対応のものが多く、スマートフォンアプリと連携可能)を使用すると、自分で車のECUにアクセスし、エラーコードを読み取ることができます。これにより、専門業者に持ち込む前に、ある程度の原因の目安をつけたり、症状の進行状況をモニターしたりすることが可能になります。
- 車両健康管理アプリ: 一部のアプリは、OBD-IIスキャナーと連携して、燃費の記録、走行データの分析、メンテナンス時期のリマインダー機能などを提供しています。これらのツールを活用することで、車の状態をより詳細に把握し、予防的なメンテナンス計画を立てるのに役立ちます。
- メンテナンスノートの活用と履歴管理の徹底:
- 詳細な記録: いつ、どのような症状が発生したか、どのような修理を行ったか、どの部品を交換したか、費用はいくらだったかなど、車のメンテナンス履歴を詳細に記録するノートを作成しましょう。
- 修理工場の情報: どの整備工場で作業を行ったか、担当整備士の名前なども記録しておくと、将来的に同じ工場に依頼する際や、別の工場に相談する際に役立ちます。
- 履歴の共有: 車を売却する際や、中古車として購入する際にも、詳細なメンテナンス履歴は車の価値を判断する重要な要素となります。
- 信頼できる整備士との関係構築:
- かかりつけ医のような存在: 車のメンテナンスは、人間の健康管理と似ています。信頼できる整備工場や特定の整備士を見つけ、車の「かかりつけ医」として定期的に相談できる関係を築くことが理想です。
- 情報共有: 些細なことでも相談できる関係があれば、早期の異常発見や適切なアドバイスを得やすくなります。車の特性や過去のトラブルを把握してもらえれば、より的確な診断と修理に繋がります。
- DIYでの簡易チェックとプロへの依頼の線引き:
- 自分でできる簡易的な点検(オイルレベル、冷却水、タイヤ空気圧、エアフィルターの目視確認など)は日常的に行い、車の状態を把握する習慣をつけましょう。
- しかし、エンジン内部や電気系統の深い部分に関わる問題、特に診断機が必要な故障については、無理せずプロに依頼する線引きを明確にすることが重要です。自己判断での無理な修理は、かえって高額な修理費用に繋がるリスクがあります。
これらの応用アイデアは、単に目の前の不具合を解決するだけでなく、長期的な視点で愛車のパフォーマンスを維持し、安全性を高めるためのものです。車の状態を「見える化」し、専門家と連携することで、より賢く、安心してカーライフを楽しむことができるでしょう。
8. 車 エンジン 回転数 不安定の徹底解説の予算と費用
エンジン回転数の不安定さに関する修理費用は、原因や車種、部品の種類、修理を依頼する工場によって大きく異なります。ここでは、一般的な費用相場と予算を立てる上でのポイントを解説します。
- 診断費用:
- ほとんどの整備工場では、まず診断機(OBD-IIスキャナー)を用いた診断を行います。
- 相場: 3,000円~10,000円程度。診断のみで原因が特定できない場合や、より詳細な点検が必要な場合は、追加費用が発生することもあります。この診断費用は、修理を依頼すれば修理費用に含まれる場合もあります。
- 部品代と工賃の目安(原因別):
- エアフィルター交換:
- 部品代: 1,000円~5,000円
- 工賃: 1,000円~3,000円(DIY可能)
- 合計: 1,000円~8,000円
- 点火プラグ交換:
- 部品代: 1本500円~2,000円(車種により本数が異なる)
- 工賃: 3,000円~10,000円(V型エンジンや直噴エンジンは高くなる傾向)
- 合計: 5,000円~20,000円
- イグニッションコイル交換:
- 部品代: 1個5,000円~15,000円(車種により本数が異なる)
- 工賃: 3,000円~15,000円
- 合計: 8,000円~30,000円(1個あたり)
- スロットルボディ清掃・調整:
- 部品代: 不要(清掃のみの場合)
- 工賃: 5,000円~15,000円
- 合計: 5,000円~15,000円
- エアフロセンサー交換:
- 部品代: 10,000円~30,000円
- 工賃: 3,000円~8,000円
- 合計: 13,000円~38,000円
- O2センサー交換:
- 部品代: 10,000円~40,000円
- 工賃: 5,000円~15,000円
- 合計: 15,000円~55,000円
- 燃料ポンプ交換:
- 部品代: 20,000円~80,000円
- 工賃: 10,000円~30,000円
- 合計: 30,000円~110,000円
- インジェクター交換:
- 部品代: 1本10,000円~50,000円(車種により本数が異なる)
- 工賃: 10,000円~50,000円
- 合計: 20,000円~100,000円(1本あたり)
- ECU(エンジンコントロールユニット)交換:
- 部品代: 50,000円~200,000円以上
- 工賃: 10,000円~50,000円
- 合計: 60,000円~250,000円以上(最も高額になるケース)
- 予算を立てる上でのポイント:
- 複数の見積もり: 複数の整備工場から見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。ただし、安さだけで選ばず、診断内容や説明の丁寧さも考慮しましょう。
- 純正部品か社外品か: 部品には純正品と社外品(OEM品やリビルド品)があり、価格が大きく異なります。社外品は安価ですが、品質や耐久性について整備士とよく相談しましょう。
- DIYとプロの費用対効果: エアフィルター交換など簡単な作業はDIYで費用を抑えられますが、専門的な修理はプロに任せる方が結果的に安く済むことが多いです。誤ったDIYで別の部品を壊すと、かえって高額な出費になります。
- 緊急性と優先順位: 走行に支障がある、安全に関わる不具合は最優先で修理すべきです。燃費悪化など、すぐに危険ではないが放置すると悪化する可能性のあるものは、計画的に修理を検討しましょう。
エンジン回転数の不安定さは原因が多岐にわたるため、費用も大きく変動します。まずは正確な診断を受け、その上で修理内容と費用について十分に説明を受け、納得した上で作業を依頼することが重要です。
まとめ:車 エンジン 回転数 不安定の徹底解説を成功させるために
車のエンジン回転数が不安定になる症状は、単なる不快感ではなく、愛車の健康状態を示す重要なサインです。この記事では、その基本から種類、自分でできる初期診断、具体的な実践方法、注意点、予防のコツ、応用アイデア、そして修理にかかる費用まで、徹底的に解説してきました。
この症状の原因は、燃料、吸気、点火、排気、電気系統、センサー、ECUなど、多岐にわたります。そのため、症状を正確に把握し、適切な診断を行うことが、問題解決への第一歩となります。自分でできる簡単なチェックはありますが、根本的な原因の特定や修理には、専門的な知識と経験、そして専用の診断ツールが不可欠です。
最も重要なことは、症状を放置しないことです。燃費の悪化、排ガスの増加、エンジンの寿命短縮、そして何よりも走行中のエンストや事故のリスクを避けるためにも、異変を感じたらすぐに信頼できる整備工場に相談しましょう。
日頃からの定期的なメンテナンス、五感を研ぎ澄ませた異常の早期発見、そして信頼できる整備士との関係構築が、愛車と長く安全に付き合っていくための鍵となります。この記事が、あなたの愛車のエンジン回転数不安定の問題解決の一助となり、より快適で安全なカーライフを送るための一助となれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
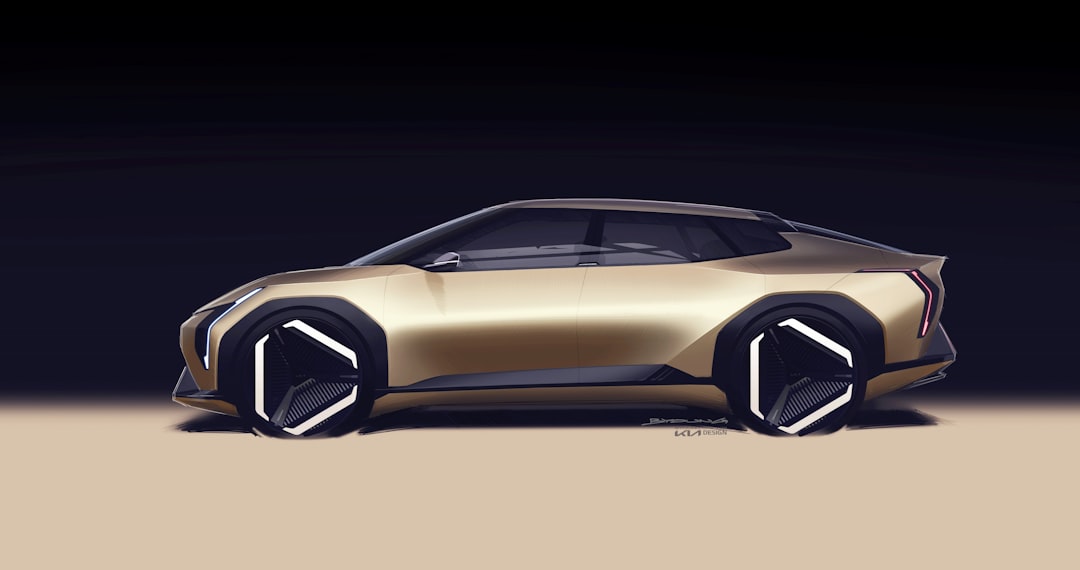
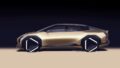
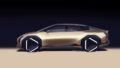
コメント