車 ライト 車検対応の完全ガイド

夜間や悪天候時の視界確保、そして周囲への意思表示。車のライトは、安全運転に欠かせない重要な保安部品です。しかし、見た目を良くしたい、もっと明るくしたいとカスタムを施した結果、「車検に通らない」という事態に陥るドライバーも少なくありません。車のライトは、その種類や取り付け方、明るさ、色に至るまで、国の定める「保安基準」によって厳しく規定されています。
この記事では、車のライトが車検に対応するための詳細な知識を、基本から応用、そして費用面まで徹底的に解説します。愛車のカスタムを楽しみたい方も、車検を控えている方も、この完全ガイドを読めば、安心してカーライフを送るためのヒントが必ず見つかるでしょう。
1. 車 ライト 車検対応の基本

車のライトが車検に対応しているかどうかは、車両の安全性を確保し、公道を走行する上で非常に重要な要素です。車検(自動車検査登録制度)は、自動車が国の定める「保安基準」に適合しているかを定期的に確認する制度であり、この保安基準にはライトに関する詳細な規定が含まれています。これらの基準を満たしていなければ、車検に合格することはできません。
⚠️ 重要情報:車検でチェックされるライトの基本項目
車のライトに関する保安基準は多岐にわたりますが、特に重要なのは以下の5点です。
- 色(光色): 各ライトには定められた光色があります。
- ヘッドライト(前照灯): 白色。淡黄色も認められますが、現在は白色が主流です。
- フォグランプ(前部霧灯): 白色または淡黄色。
- ポジションランプ(車幅灯): 白色、淡黄色、橙色。
- ウインカー(方向指示器): 橙色。
- テールランプ(尾灯): 赤色。
- ストップランプ(制動灯): 赤色。
- バックランプ(後退灯): 白色。
- ナンバー灯(番号灯): 白色。
規定外の色(青色、緑色など)のライトは、たとえわずかな色味であっても車検不合格となります。
- 明るさ(光度): ライトの明るさには、最低限度と上限が定められています。
- ヘッドライト: ロービームで6,400カンデラ(cd)以上、ハイビームで15,000カンデラ(cd)以上が必要です。また、ハイビームの上限は225,000カンデラ(cd)と定められており、あまりに明るすぎても車検に通りません。これは対向車への幻惑を防ぐためです。
- その他のライトも、視認性確保と眩惑防止の観点から適切な明るさが求められます。極端に暗いものや、後付けで非常に明るすぎるものは不合格となる可能性があります。
- 光軸(照射方向): ヘッドライトの光がどの方向を照らしているかは非常に重要です。
- 光軸は、路面を適切に照らし、同時に前方車両や対向車のドライバーを眩惑させないように調整されていなければなりません。少しでもズレていると車検不合格となります。特にロービームの光軸は厳しく、専用のテスターを用いた精密な調整が必要です。
- 数と取り付け位置: 各ライトの数と取り付け位置も規定されています。
- ヘッドライト: 左右対称に2個。
- フォグランプ: 左右対称に2個まで。ヘッドライトより下に取り付けられている必要があります。
- ウインカー: 前後左右に各1個以上(合計4個以上)。点滅回数も1分間に60回以上120回以下と定められています。
- テールランプ: 左右対称に2個。
- ストップランプ: 左右対称に2個。ハイマウントストップランプは1個まで。
- その他、車両の中心線からの距離、地上高など、細かな規定があります。
- 点灯状態: すべてのライトが正常に点灯し、消灯すること。
- 接触不良による点滅、不点灯、球切れなどはすべて不合格の原因となります。
これらの基本を理解することが、車検対応のライト選びとメンテナンスの第一歩となります。安全性と法規制を無視したカスタムは、車検不合格だけでなく、事故や罰則につながる危険性があることを常に念頭に置きましょう。
2. 車 ライト 車検対応の種類

車のライトは一言で言っても多種多様であり、それぞれに異なる役割と車検基準が設けられています。カスタムを行う際は、これらのライトの種類ごとの規定を正確に理解しておくことが不可欠です。
💡 重要ポイント:主要なライトの種類と車検基準
- ヘッドライト(前照灯)
- 役割: 夜間やトンネル内での前方視界確保。ハイビーム(走行用前照灯)とロービーム(すれ違い用前照灯)があります。
- 車検基準:
- 色: 白色(淡黄色も可)。
- 光度: ロービーム6,400cd以上、ハイビーム15,000cd以上225,000cd以下。
- 光軸: 最も厳しくチェックされる項目。対向車を眩惑させない「カットライン」が明確であること。
- 数: 左右対称に2個。
- カスタムの注意点: ハロゲンからHIDやLEDに交換する際、色温度(ケルビン数)が6,000K程度までが一般的で、高すぎると青みがかって車検不合格になることがあります。また、バルブ交換だけでなく、ユニット全体を交換する際は、その製品がEマーク(欧州統一基準適合)やJISマーク(日本工業規格適合)などの認証を受けているか確認しましょう。安価な製品は光軸が出ない、カットラインが不明瞭などの問題が発生しやすいです。
- フォグランプ(前部霧灯)
- 役割: 霧や豪雨など悪天候時の視界補助。
- 車検基準:
- 色: 白色または淡黄色。
- 数: 2個まで。
- 取り付け位置: ヘッドライトより低い位置に、左右対称に取り付ける必要があります。地上高250mm以上、800mm以下。
- カスタムの注意点: ヘッドライト同様、色温度に注意。点灯スイッチが独立しており、ヘッドライトと同時に点灯・消灯できること(単独点灯・消灯も可)が求められます。
- テールランプ(尾灯)
- 役割: 夜間、後方車両に自車の存在を示す。
- 車検基準:
- 色: 赤色。
- 数: 左右対称に2個。
- 明るさ: 夜間後方から確認できる適切な明るさ。ストップランプより暗いこと。
- カスタムの注意点: スモーク加工などで透過率が落ちると、光度が不足して車検不合格となることがあります。LED化の際は、粒々に見えない「面発光」タイプや、均一に光るものが人気ですが、明るさや色の基準を満たしているか確認が必要です。
- ストップランプ(制動灯)
- 役割: ブレーキ作動時に後方車両に減速・停止を知らせる。
- 車検基準:
- 色: 赤色。
- 数: 左右対称に2個。ハイマウントストップランプは1個まで。
- 明るさ: テールランプより明らかに明るいこと。
- カスタムの注意点: 点滅機能付きは車検不合格となります。ハイマウントストップランプも、点滅したり、色が変わったりするものはNGです。
- ウインカー(方向指示器)
- 役割: 車線変更や右左折時に進行方向を周囲に知らせる。
- 車検基準:
- 色: 橙色。
- 点滅回数: 1分間に60回以上120回以下。
- 数: 前後左右に各1個以上。
- カスタムの注意点: 最近流行の「シーケンシャルウインカー(流れるウインカー)」は、国土交通省の定める基準(内側から外側へ順次点灯し、全体が同時に消灯することなど)を満たしていれば車検対応です。ただし、必ず「車検対応品」を選ぶことが重要です。抵抗値の合わないLEDバルブに交換すると、点滅が速くなる「ハイフラッシャー現象」が起き、車検不合格となります。
- ポジションランプ(車幅灯)
- 役割: 夜間、前方から車両の幅を示す。
- 車検基準:
- 色: 白色、淡黄色、橙色。ヘッドライトやフォグランプと異なる色でも可。
- 数: 2個。
- 明るさ: 夜間前方から確認できる明るさで、ヘッドライトを眩惑しない程度。
- カスタムの注意点: 青色や紫色など、規定外の色は不合格。明るすぎてもNGです。
- ライセンスランプ(ナンバー灯)
- 役割: 夜間、ナンバープレートを照らし、識別を可能にする。
- 車検基準:
- 色: 白色。
- 明るさ: ナンバープレートの文字が鮮明に判別できること。
- カスタムの注意点: 青みがかったLEDなどは不合格になることがあります。
これらのライトの種類ごとの基準を把握し、信頼できる「車検対応品」を選ぶことが、安全かつ合法的なカスタムを楽しむための鍵となります。
3. 車 ライト 車検対応の始め方

車のライトを車検対応の状態に保つためには、日頃からの意識と適切な準備が重要です。特に、カスタムを検討している場合や、車検が近づいている場合は、計画的に進める必要があります。
📌 注目点:車検対応ライトの始め方と準備
- 自己診断で現状を把握する
まずは、ご自身の車のライトがどのような状態にあるかを自身で確認することから始めましょう。
- 外観チェック: ライトのレンズにひび割れ、傷、曇り、黄ばみ、水滴の侵入がないか確認します。これらは光量低下や光軸のズレの原因となります。
- 点灯チェック: すべてのライト(ヘッドライト、フォグランプ、テールランプ、ストップランプ、ウインカー、ポジションランプ、バックランプ、ナンバー灯)が正常に点灯するか、左右で明るさに差がないかを確認します。家族や友人に協力してもらい、ブレーキペダルを踏んだり、ウインカーを出したりしてもらいましょう。
- 色の確認: 各ライトの色が規定通りか、目視で確認します。特にLEDバルブなどに交換している場合は、色温度が高すぎて青みがかっていないか注意が必要です。
- 明るさの感覚チェック: 極端に暗い、または眩しすぎるライトがないか、感覚的に確認します。これはあくまで目安ですが、異常に気づくきっかけになります。
- 信頼できる製品の選び方
カスタムや交換を行う際には、製品選びが最も重要です。
- 「車検対応」表示の確認: 最も基本的なことですが、製品パッケージや説明書に「車検対応」と明記されていることを確認しましょう。ただし、この表示があっても、取り付け方や車両との相性によっては車検に通らないケースもあるため、過信は禁物です。
- Eマーク/JISマークの有無: 国際基準や国内基準に適合していることを示す「Eマーク」や「JISマーク」が付いている製品は、品質と信頼性が高いと言えます。特にヘッドライトユニットなどの大型部品では、これらの認証が重要になります。
- メーカーの信頼性: 無名ブランドの安価な製品は、初期不良や耐久性の問題、さらには保安基準を満たしていない可能性も高いため、大手メーカーや実績のあるブランドの製品を選ぶのが賢明です。
- 色温度(ケルビン数): HIDやLEDバルブの場合、色温度は6000K(ケルビン)程度までが、白色として車検に通りやすい範囲です。それ以上になると青みが強くなり、不合格のリスクが高まります。
- 光度(カンデラ数): ヘッドライトの光度は特に重要です。製品によってはカンデラ数が記載されているものもありますが、実際に取り付けた状態で測定しないと正確な値は分かりません。
- 専門業者への相談と依頼
ライトに関する知識や交換作業に不安がある場合は、迷わずプロに相談しましょう。
- ディーラー: 純正部品や純正同等品の交換、正確な光軸調整など、最も確実な選択肢です。ただし、費用は高めになる傾向があります。
- 整備工場: 経験豊富な整備士が、車種に応じたアドバイスや適切な交換作業を行ってくれます。カスタムパーツの持ち込み取り付けに対応してくれる場合もあります。
- カー用品店: ライト関連の製品が豊富に揃っており、専門スタッフが相談に乗ってくれます。取り付け作業も依頼できることが多いです。
- 光軸調整: ヘッドライトの光軸調整は、専用のテスターがなければ正確に行うことはできません。DIYでの簡易調整はあくまで応急処置と考え、車検前には必ず専門業者で正確に調整してもらいましょう。
- DIY交換の際の注意点
バルブ交換など簡単な作業であればDIYも可能ですが、以下の点に注意が必要です。
- 車種別適合: 自分の車種に合ったバルブの種類(H4、H7など)やワット数を確認します。
- 工具の準備: 交換に必要な工具(ドライバー、レンチなど)を揃え、取扱説明書をよく読みましょう。
- 安全確保: 作業前にエンジンを停止し、バッテリーのマイナス端子を外すなど、感電や火傷のリスクを避けるための対策を講じます。
- 防水処理: 交換後は、水滴が内部に侵入しないよう、しっかりと防水処理を行うことが重要です。
- 点灯確認: 交換後、すべてのライトが正常に点灯するか、改めて確認します。
これらのステップを踏むことで、安心して車検対応のライトを使用し、安全なカーライフを送ることができます。
4. 車 ライト 車検対応の実践

車のライトを車検対応の状態にするための準備が整ったら、いよいよ実践です。ここでは、具体的なライトの交換作業や、車検合格に不可欠な光軸調整、そして車検当日の流れについて解説します。
ライト交換作業の流れ
純正のハロゲンバルブからHIDやLEDへの交換、あるいはユニット全体の交換など、ライトのカスタムは多岐にわたります。ここでは一般的なバルブ交換とユニット交換のポイントを説明します。
- バルブ交換(HID/LED化)
- 純正ハロゲンバルブの取り外し: 多くの車種では、ボンネットを開けてヘッドライトユニット裏側からバルブにアクセスできます。防水カバーを外し、コネクタを抜いて、固定バネを解除すればバルブが取り外せます。
- HID/LEDバルブの取り付け:
- HIDの場合: バルブ、バラスト、イグナイターの3点セットが基本です。バルブをユニットに取り付け、バラストとイグナイターはエンジンの熱や水から保護できる適切な場所(バンパー裏やフェンダー内部など)に固定します。配線はカプラーオンが主流ですが、一部加工が必要な場合もあります。
- LEDの場合: バルブ本体にドライバーユニットが内蔵されている一体型と、別体型があります。一体型は比較的簡単に交換できます。別体型の場合は、ドライバーユニットを熱や水の影響を受けにくい場所に固定します。
- 共通の注意点: バルブのガラス部分には素手で触れないようにしましょう(油分が付着すると寿命が縮まる原因に)。配線は確実に接続し、防水処理(ゴムキャップの密着、コーキングなど)を怠らないことが重要です。また、車種によっては冷却ファンやヒートシンクが干渉して取り付けできない場合もあるため、事前に確認が必要です。
- ユニット交換(ヘッドライト/テールランプ)
- 既存ユニットの取り外し: バンパーやフェンダーの一部を取り外す必要がある場合が多いです。固定されているボルトやクリップを外し、配線コネクタを慎重に抜いて、ユニットを取り外します。
- 新しいユニットの取り付け: 新しいユニットを逆の手順で取り付けます。取り付けネジの締め付けは均等に行い、隙間やガタつきがないか確認します。
- 配線の接続: 新しいユニットの配線を車両側のハーネスに接続します。社外品の場合、カプラーオンで接続できるものが多いですが、一部車種では配線加工が必要な場合もあります。
- 注意点: ユニット交換はバルブ交換よりも大掛かりな作業となるため、自信がない場合はプロに依頼するのが賢明です。特にヘッドライトユニットを交換した場合は、必ず光軸調整が必要になります。
光軸調整の重要性
ヘッドライトの光軸調整は、車検合格の最重要ポイントの一つです。光軸がずれていると、路面を適切に照らせず安全性が損なわれるだけでなく、対向車を眩惑させて事故を誘発する危険性があります。
- 簡易的な光軸調整(DIY):
- 平坦な場所に車を停め、壁から約10m離れた位置に設置します。
- ヘッドライトを点灯させ、壁に映る光のカットライン(光と影の境目)を確認します。
- 車種ごとの基準値(例:ロービームのカットラインが地上から約60cm~90cmの範囲で、水平な部分が車両中心から左にずれているなど)を参考に、ヘッドライトユニットにある調整ネジ(上下・左右)を回して調整します。
- 注意点: この方法はあくまで簡易的な目安であり、正確な調整はできません。車検合格のためには、専門業者での調整が必須です。
- 専門業者での光軸調整:
- ディーラー、整備工場、カー用品店などでは、専用の「ヘッドライトテスター」を用いて光軸を精密に測定・調整します。
- テスターは、光度も同時に測定できるものが多く、車検基準に適合しているかを正確に判断できます。
- 費用は数千円程度が一般的で、車検前には必ず依頼することをお勧めします。
車検時のチェックポイント
車検当日は、検査官が以下の点を中心にライトをチェックします。
- 目視確認:
- すべてのライトが正常に点灯・消灯するか。
- ライトの色が規定通りか(青みや黄みが強すぎないか)。
- レンズに破損や著しい曇りがないか。
- 取り付け位置や数が保安基準に適合しているか。
- ウインカーの点滅回数が適切か。
- テスターによる測定:
- ヘッドライトの光度(明るさ)が基準値内か。
- ヘッドライトの光軸が正確か。
これらの実践ポイントを押さえることで、安心して車検に臨むことができるでしょう。
5. 車 ライト 車検対応の注意点
車のライトのカスタムや交換を検討する際、最も重要なのが「車検対応」であるか否かです。安易な選択は、金銭的な負担だけでなく、安全面や法的なリスクを伴う可能性があります。
非対応品使用のリスク
車検対応ではないライトを使用することには、様々なリスクが伴います。
- 車検不合格: 最も直接的なリスクです。車検に通らなければ、公道を走行することはできません。再検査の費用や手間が発生し、車検切れのリスクも生じます。
- 罰則・違法改造: 保安基準に適合しないライトは「整備不良」または「違法改造」とみなされ、検挙の対象となります。
- 整備不良: 交通違反となり、点数や反則金が科せられます。例えば、ヘッドライトの光度不足や光軸不良、色の不適合などが該当します。
- 違法改造: 悪質な場合は、車両の使用停止命令や罰金が科せられることもあります。
- 事故のリスク:
- 視認性不足: 暗すぎるライトや、照射範囲が不適切なライトは、夜間や悪天候時の視界を著しく損ない、事故につながる危険性があります。
- 対向車への幻惑: 明るすぎるライトや、光軸が上向きにずれているライトは、対向車や先行車のドライバーを眩惑させ、事故を誘発する可能性があります。
- 保険適用外: 違法改造車と判断された場合、万が一事故を起こした際に任意保険が適用されない可能性もゼロではありません。これは非常に大きなリスクです。
- 車両への悪影響: 安価な非対応品は、車両の電装系に過度な負荷をかけたり、防水性が不十分でショートや火災の原因になったりする可能性もあります。また、純正部品の保証が無効になることもあります。
安価な製品の落とし穴
インターネット通販などで見かける極端に安価なライト製品には、注意が必要です。
- 品質の低さ: 耐久性が低く、すぐに球切れや故障が発生しやすいです。また、色ムラがあったり、光量が不安定だったりすることもあります。
- 保安基準不適合: 「車検対応」と謳っていても、実際には光度不足、色温度の不適合、光軸が出ない、カットラインが不明瞭といった理由で車検に通らないケースが多々あります。
- 防水性・放熱性の不足: 内部に水が浸入しやすく、ショートの原因となったり、LEDチップの過熱による寿命短縮や故障につながったりします。
- 誤った情報: 製品説明に虚偽の情報が記載されていることもあり、消費者が誤って購入してしまうケースも少なくありません。
誤った情報の見分け方と法改正への対応
- 情報源の確認: インターネット上には様々な情報が溢れていますが、そのすべてが正しいとは限りません。国土交通省の公式サイトや、信頼できる自動車メーカー、大手カー用品店、専門誌などの情報を参考にしましょう。個人ブログや掲示板の情報は、あくまで参考程度にとどめるのが賢明です。
- 「車検対応」の真偽: 「車検対応」と表示されていても、その根拠(Eマーク、JISマーク、メーカーのテストデータなど)が不明確な製品は避けるべきです。特に、極端に明るいものや、特殊な色のものは、慎重に確認が必要です。
- 法改正への対応: 自動車の保安基準は、安全性の向上や新技術の導入に伴い、不定期に改正されることがあります。例えば、デイライト(昼間走行灯)やシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)に関する基準も近年変更されました。常に最新の保安基準情報を確認し、自分の車のライトが現在の基準に適合しているかを把握しておくことが重要です。
これらの注意点を踏まえ、安易な選択を避け、信頼できる製品と情報を基に、安全で合法的なカーライフを送りましょう。
6. 車 ライト 車検対応のコツ
車のライトを車検対応の状態に保ち、さらに安全で快適なカーライフを送るためには、日頃からのちょっとした心がけと、プロの知識を活用するコツがあります。
長持ちさせるためのメンテナンス
ライトの寿命を延ばし、常に最高のパフォーマンスを発揮させるためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。
- 定期的な点検:
- バルブの点灯確認: すべてのライトが正常に点灯するか、週に一度は確認しましょう。特にヘッドライトやテールランプは、片側が切れていても気づきにくいことがあります。
- レンズの確認: ヘッドライトやテールランプのレンズに、ひび割れ、傷、曇り、黄ばみがないか確認します。これらは光量低下や光軸のズレの原因となります。
- 配線の確認: バルブやユニット周辺の配線が緩んでいないか、被膜が破れていないかなどを確認します。接触不良やショートを防ぐためです。
- レンズの清掃と保護:
- 定期的な清掃: ライトのレンズは走行中に泥や虫の死骸などで汚れやすい部分です。定期的に柔らかい布と中性洗剤で優しく洗い、常にクリアな状態を保ちましょう。
- ヘッドライトクリーナー・コーティング: 長年使用していると、紫外線や熱によってヘッドライトのレンズが黄ばんだり曇ったりすることがあります。市販のヘッドライトクリーナーで磨き、その後に専用のコーティング剤を塗布することで、透明感を回復させ、再劣化を防ぐことができます。これは光量確保の観点からも非常に重要です。
視認性を高める工夫
車検対応の範囲内で、自身の車の視認性を高める工夫も安全運転につながります。
- 高品質なバルブへの交換: 純正バルブでも、より明るく、耐久性の高い「高効率ハロゲンバルブ」や、純正同等の色温度で明るさを向上させた「車検対応LEDバルブ」に交換することで、夜間の視界を改善できます。
- 対向車への配慮: 自分の視界を確保することも大切ですが、対向車や先行車を眩惑させない配慮も忘れてはなりません。光軸がずれていないか定期的に確認し、必要であれば調整を行いましょう。また、不必要なフォグランプの使用は避けましょう。
プロのアドバイス活用法
専門家の知識と技術を活用することは、間違いのないライト選びとメンテナンスにつながります。
- 整備士やカー用品店スタッフへの相談:
- 「自分の車種に合った車検対応のライトはどれか?」「どのメーカーの製品が信頼できるか?」といった疑問は、プロに直接相談するのが最も確実です。
- 取り付け作業や光軸調整についても、費用や所要時間などを事前に確認し、依頼しましょう。
- 特に、HIDやLEDへの交換は車種によって取り付けの難易度や適合が異なるため、プロの意見を聞くことが重要です。
- 車検前の事前点検: 車検前にディーラーや整備工場でライトの事前点検を依頼することで、不合格になるリスクを大幅に減らすことができます。光軸調整なども同時に依頼できるため、一石二鳥です。
情報収集の習慣
自動車の技術や法規は常に進化しています。最新情報をキャッチアップする習慣をつけましょう。
- 新製品情報のチェック: 各メーカーから常に新しい技術や製品がリリースされています。車検対応品の中で、より高性能なものや、デザイン性の高いものがないか、定期的に情報収集しましょう。
- 法改正情報の確認: 自動車の保安基準は、安全性の向上や国際基準との整合性のために変更されることがあります。国土交通省のウェブサイトや自動車関連のニュースサイトなどで、常に最新の法改正情報を確認する習慣をつけましょう。
- オーナーズクラブや専門フォーラム: 同じ車種のオーナーが集まるオンラインコミュニティやフォーラムでは、具体的な製品のインプレッションや、DIYのヒント、車検に関する体験談など、生きた情報が得られることがあります。ただし、情報の真偽は自身で判断する必要があります。
これらのコツを実践することで、愛車のライトを常に最適な状態に保ち、安全で快適なドライブを楽しむことができるでしょう。
7. 車 ライト 車検対応の応用アイデア
車のライトは、単なる保安部品に留まらず、車の個性やオーナーのこだわりを表現するドレスアップパーツとしても人気があります。車検基準をクリアしながら、愛車をより魅力的に見せるための応用アイデアをご紹介します。
ドレスアップと車検対応の両立
カスタムライトは見た目のインパクトが大きいですが、車検対応が大前提です。
- シーケンシャルウインカー(流れるウインカー): 近年人気の高いシーケンシャルウインカーは、内側から外側へ光が流れるように点滅するタイプです。国土交通省の保安基準が改正され、特定の条件(内側から外側へ順次点灯し、全体が同時に消灯すること、点滅周期など)を満たせば車検対応となりました。購入する際は必ず「車検対応品」であることを確認し、ECE R48(欧州ECE規則)の認証を受けている製品を選ぶと安心です。
- デザイン性の高いヘッドライト/テールライトユニット:
- イカリング、コの字型ポジションランプ: 純正品にはない独特のデザインで、車のフロントマスクを個性的に演出できます。これらは多くの場合、車検対応として設計されていますが、ポジションランプの色が白色、淡黄色、橙色のいずれかであること、明るさが眩惑しない程度であることなどが基準となります。
- フルLEDテールランプ: LEDの特性を活かした、粒々に見えない「面発光」や、立体的なデザインのテールランプユニットは
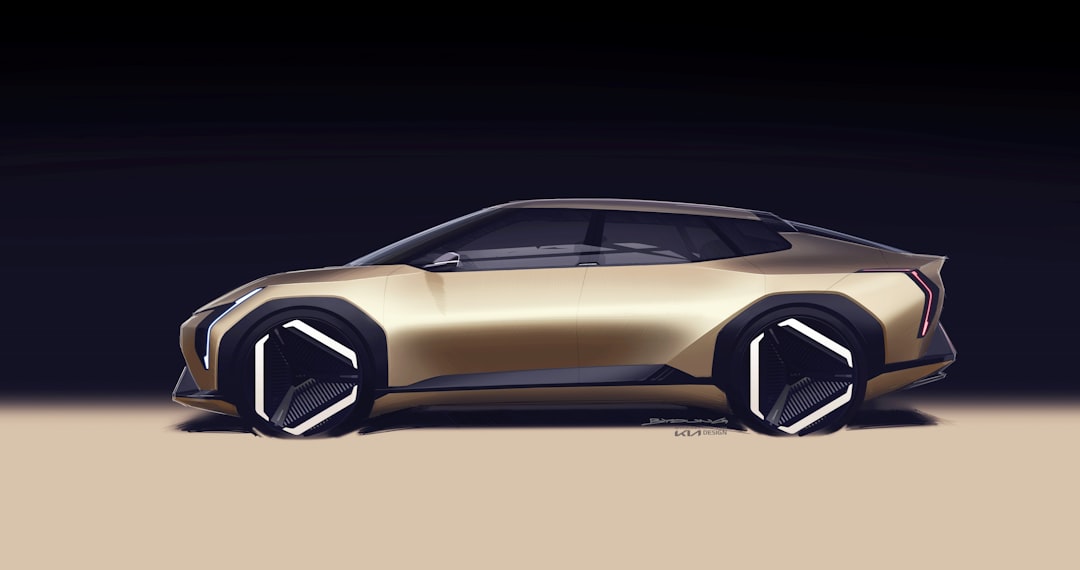

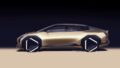
コメント