車のブレーキフルード交換 完全ガイド

車の安全を語る上で、ブレーキシステムはまさに生命線です。そして、そのブレーキシステムの中核を担うのが「ブレーキフルード」。この液体は、ドライバーがブレーキペダルを踏む力を油圧として各タイヤのブレーキキャリパーに伝え、車を安全に減速・停止させるという極めて重要な役割を担っています。しかし、ブレーキフルードは時間とともに劣化し、その性能は確実に低下していきます。劣化したフルードを使い続けることは、ブレーキの効きが悪くなるだけでなく、最悪の場合、重大な事故に繋がりかねません。
この「車のブレーキフルード交換 完全ガイド」では、なぜブレーキフルードの交換が必要なのか、どのような種類があるのかといった基本的な知識から、実際に交換作業を行う際の具体的な手順、注意点、さらにはプロに依頼する際の費用まで、ブレーキフルード交換に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。DIYでの交換を検討している方はもちろん、プロに任せる場合でも、このガイドを読めば、より安心してブレーキシステムのメンテナンスに取り組めるようになるでしょう。あなたの愛車の安全と、快適なドライブのために、ぜひ最後までお読みください。
1. 車のブレーキフルード交換 完全ガイドの基本

ブレーキフルードとは、自動車のブレーキシステムにおいて、ドライバーがブレーキペダルを踏む力を油圧としてブレーキキャリパーに伝え、摩擦によって車を減速・停止させるための作動油です。その主成分はグリコールエーテル系またはシリコン系であり、高い非圧縮性と耐熱性が求められます。このフルードが劣化すると、ブレーキの効きが悪くなったり、ペダルタッチがフワフワとした感触になったりする原因となります。
ブレーキフルードが劣化する主な原因は、「吸湿性」にあります。ブレーキフルードは非常に吸湿性が高く、空気中の水分を吸収しやすい性質を持っています。水分を吸収すると、フルードの沸点が低下します。ブレーキを多用する状況や、長時間のブレーキングによってブレーキシステムが高温になると、フルード中の水分が沸騰し、気泡(ベーパーロック)が発生します。気泡は圧縮されてしまうため、油圧が正確に伝わらなくなり、ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かなくなる「ベーパーロック現象」を引き起こし、極めて危険な状態に陥ります。
また、吸湿した水分はブレーキシステムの金属部品を錆びさせ、ゴム部品を劣化させる原因にもなります。これにより、ブレーキホースやキャリパーのシール類が損傷し、フルード漏れやブレーキの固着といったトラブルに発展する可能性もあります。
一般的に、ブレーキフルードの交換時期は、新車購入から2年ごと、または走行距離が4万kmごとが目安とされています。車検のタイミングで交換を推奨されることが多いのはこのためです。フルードの色が透明から茶色や黒っぽく変色している場合も、劣化のサインとして交換を検討するべきです。DIYでの交換はコストを抑えられるメリットがありますが、 ⚠️ ブレーキは車の安全に直結する最重要部品です。交換作業には専門的な知識と適切な工具、そして細心の注意が求められます。少しでも不安がある場合は、迷わずプロの整備士に依頼することが、何よりも安全を確保するための「重要情報」となります。
2. 車のブレーキフルード交換 完全ガイドの種類

ブレーキフルードにはいくつかの種類があり、それぞれ異なる特性を持っています。これらの種類は「DOT(Department of Transportation)」規格によって分類され、DOT3、DOT4、DOT5、DOT5.1といった表記が一般的です。自分の車に適合しないフルードを使用すると、ブレーキシステムの性能低下や故障に繋がるため、正しい選択が非常に重要です。
- DOT3: 最も一般的なブレーキフルードで、グリコールエーテル系を主成分とします。比較的安価で、多くの一般乗用車に採用されています。乾燥沸点は205℃以上、ウェット沸点は140℃以上と定められています。吸湿性が高く、定期的な交換が必要です。
- DOT4: DOT3よりも沸点が高く、より高性能なブレーキフルードです。乾燥沸点は230℃以上、ウェット沸点は155℃以上と定められており、スポーツ走行や重い車両など、ブレーキに高い負荷がかかる車に適しています。DOT3と同様にグリコールエーテル系で、DOT3との混用も可能ですが、性能は低い方に合わせられます。
- DOT5.1: DOT4よりもさらに高性能で、乾燥沸点は260℃以上、ウェット沸点は180℃以上と非常に高い沸点を持っています。これもグリコールエーテル系であり、DOT3やDOT4との互換性があります。主に高性能車や競技車両などで使用されます。
- DOT5: 他のDOT規格とは異なり、シリコン系の成分を主成分としています。乾燥沸点は260℃以上、ウェット沸点は180℃以上と高い沸点を持つ点が特徴です。最大の利点は「非吸湿性」であることです。水分を吸収しないため、ブレーキシステムの錆を防ぎ、長期間性能を維持できます。しかし、シリコン系はグリコール系とは全く異なる性質を持つため、💡 DOT3、DOT4、DOT5.1とは絶対に混用できません。混用すると、ブレーキシステムのゴム部品が劣化したり、フルードが分離してブレーキが効かなくなるなど、重大な故障を引き起こす危険性があります。DOT5は主にクラシックカーや軍用車両など、特定の用途で使用されることが多く、一般の乗用車ではほとんど使用されません。もしDOT5を使用している車であれば、その旨が明確に表示されているはずです。
ご自身の車にどのDOT規格のブレーキフルードが指定されているかは、車両の取扱説明書やマスターシリンダーのリザーバータンクキャップに記載されています。必ず指定された規格のフルードを使用し、誤った選択をしないように注意してください。特に、グリコール系とシリコン系の違いは決定的な「重要ポイント」であり、混用は絶対に避けるべきです。
3. 車のブレーキフルード交換 完全ガイドの始め方

ブレーキフルードの交換作業を始める前に、適切な準備と安全対策を行うことが極めて重要です。これらの準備を怠ると、作業の効率が落ちるだけでなく、事故や車両の損傷に繋がる可能性もあります。
まず、作業場所の確保です。車をジャッキアップし、安定して保持する必要があるため、平坦で固い地面の上で作業を行いましょう。ガレージや整備工場のような場所が理想的です。次に、必要な工具と材料を揃えます。
必要な工具・材料リスト:
- 新しいブレーキフルード: 車の指定規格に合ったものを十分な量(通常1〜2L程度)用意します。
- ジャッキとリジットラック(馬): 車体を安全に持ち上げ、保持するために必須です。📌 リジットラックの使用は安全確保の「注目点」であり、ジャッキのみでの作業は絶対に避けてください。
- ホイールレンチ: タイヤを取り外すために必要です。
- メガネレンチまたはソケットレンチ: ブリーダーバルブの開閉に使用します。サイズは車両によって異なります(例: 8mm, 10mm)。
- 廃油受け: 排出される古いブレーキフルードを受け止めます。
- 透明なホース: ブリーダーバルブに取り付け、フルードの排出状況(気泡の有無)を確認できるようにします。
- ワンウェイバルブ付きフルードブリーダーキット(オプション): 一人での作業を楽にするツールです。
- トルクレンチ: ブリーダーバルブやホイールナットの締め付けトルクを管理するために使用します。
- ブレーキクリーナー: フルードが飛び散った際の拭き取りや、作業後の清掃に使用します。
- ウエス、使い捨て手袋、保護メガネ: フルードは塗装を傷め、皮膚に刺激を与えるため、保護具は必須です。
- 注射器またはフルード抜き取りポンプ: リザーバータンクの古いフルードを抜き取る際に便利です。
- 輪止め: ジャッキアップする前に、車が動かないように固定します。
作業開始前のチェックリスト:
- 車両の取扱説明書の確認: ブレーキフルードの指定規格、推奨交換時期、ブリーダーバルブの締め付けトルクなどを確認します。
- 作業場所の確保: 平坦で安全な場所を選び、車を固定します(サイドブレーキ、輪止め)。
- 安全対策: 保護メガネ、手袋を着用します。ブレーキフルードは塗装面を侵食するため、車体への付着に注意し、万が一付着した場合はすぐに水で洗い流すか、ブレーキクリーナーで拭き取ります。
- 古いフルードの抜き取り: まず、マスターシリンダーのリザーバータンクから、注射器などで古いフルードを可能な限り抜き取ります。これは、新しいフルードを効率的に循環させるための準備です。
- 新しいフルードの補充: 抜き取った分だけ、新しいフルードをリザーバータンクに補充し、上限レベルまで満たします。
これらの準備が整ったら、いよいよ実際の交換作業へと進みます。
4. 車のブレーキフルード交換 完全ガイドの実践

準備が整ったらいよいよ実践です。ブレーキフルードの交換作業は、一般的にマスターシリンダーから最も遠いブレーキキャリパーから順に行い、徐々に近い方へ進めていくのが効率的とされています。これは、古いフルードを完全に排出し、新しいフルードを行き渡らせるためです。通常、右後輪 → 左後輪 → 右前輪 → 左前輪 の順序で行います。
実践手順:
- 車体のジャッキアップとタイヤの取り外し:
- 車体をジャッキアップし、リジットラックで安全に支持します。
- 交換作業を行う箇所のタイヤを取り外します。
- ブリーダーバルブへのホース取り付け:
- ブレーキキャリパーまたはドラムブレーキのホイールシリンダーにあるブリーダーバルブのゴムキャップを外し、適切なサイズのメガネレンチをセットします。
- その上から透明なホースをしっかり差し込み、ホースのもう一方の端を廃油受けに入れます。
- フルードの排出とエア抜き(二人作業の場合):
- 役割分担: 一人は運転席でブレーキペダル操作、もう一人は各タイヤのブリーダーバルブ操作とフルード監視を行います。
- ペダル操作者: 「踏んで!」の合図でブレーキペダルをゆっくりと奥まで踏み込み、そのまま保持します。
- バルブ操作者: ペダルが踏み込まれた状態で、ブリーダーバルブを緩めます(半周~1周程度)。古いフルードがホースを通って廃油受けに排出されます。この際、気泡が出ていないかよく確認します。
- バルブ操作者: フルードの排出が止まったら、ブリーダーバルブをしっかりと締めます。
- ペダル操作者: 「離して!」の合図でブレーキペダルをゆっくりと元に戻します。
- この一連の動作を、排出されるフルードに気泡が混じらなくなり、新しいフルードの色(通常は透明か薄い黄色)に変わるまで繰り返します。
- リザーバータンクのフルードレベル監視と補充:
- エア抜き作業中は、マスターシリンダーのリザーバータンクのフルードレベルが「MIN(最小)」を下回らないように常に監視し、新しいフルードを適宜補充してください。フルードレベルが下がりすぎると、空気を吸い込み、ブレーキシステムにエアを噛ませてしまう可能性があります。
- 他のタイヤの作業:
- 一つのタイヤの作業が完了したら、ブリーダーバルブを規定トルクで締め付け、ゴムキャップを取り付けます。
- 次に、上記3~5の手順を、マスターシリンダーから遠い順に他のタイヤについても繰り返します。
- 最終確認:
- 全てのタイヤのフルード交換とエア抜きが完了したら、リザーバータンクのフルードレベルを再度確認し、上限まで補充します。
- 全てのブリーダーバルブがしっかり締まっているか、フルード漏れがないかを目視で確認します。
- タイヤを取り付け、規定トルクでホイールナットを締め付けます。
- 車体をジャッキから降ろします。
この実践解説を参考に、慎重かつ確実に作業を進めてください。特にエア抜きは、ブレーキの効きに直結するため、気泡が完全に出なくなるまで丁寧に行うことが重要です。
5. 車のブレーキフルード交換 完全ガイドの注意点
ブレーキフルードの交換作業は、車の安全に直結する重要なメンテナンスです。そのため、いくつかの注意点を守ることが不可欠です。これらの点を怠ると、ブレーキシステムの故障や、人身事故、車両損傷に繋がりかねません。
- ブレーキフルードの取り扱い:
- 塗装面への付着: ブレーキフルードは車の塗装を強力に侵食します。万が一、車体にフルードが付着した場合は、すぐに大量の水で洗い流すか、ブレーキクリーナーで拭き取ってください。
- 皮膚への刺激: フルードは皮膚に触れると刺激を与えることがあります。作業中は必ず使い捨て手袋や保護メガネを着用し、皮膚に付着した場合は石鹸でよく洗い流してください。
- 誤飲の危険: 小さな子供やペットの手の届かない場所に保管し、絶対に誤飲しないように注意してください。
- エア噛みの防止:
- ブレーキシステムに空気が混入する「エア噛み」は、ブレーキの効きを著しく低下させ、ペダルが底まで沈むような状態(スポンジーなペダルタッチ)を引き起こします。
- 作業中はマスターシリンダーのリザーバータンクのフルードレベルを常に監視し、MINレベルを下回らないように頻繁に補充してください。これが最も重要なエア噛み防止策です。
- エア抜きは、気泡が完全に出なくなるまで丁寧に行いましょう。
- ブリーダーバルブの取り扱い:
- 締め付けトルク: ブリーダーバルブは、締め付けすぎると破損し、緩すぎるとフルード漏れやエア噛みの原因となります。必ず規定トルクで締め付けるようにしてください。トルクレンチの使用を強く推奨します。
- 固着: 長期間開閉されていないブリーダーバルブは固着していることがあります。無理に力を加えると破損する恐れがあるため、浸透潤滑剤を塗布し、時間を置いてから慎重に作業してください。
- 廃油の適切な処理:
- 使用済みのブレーキフルードは、環境に有害な産業廃棄物です。一般ごみとして捨てることはできません。
- ガソリンスタンドやカー用品店、整備工場などで引き取ってもらうか、自治体の指示に従って適切に処理してください。廃油処理箱などを利用するのも良いでしょう。
- 作業後の確認と試運転:
- 全ての作業が完了したら、ブレーキペダルを数回踏み込み、ペダルタッチがしっかりしているか、底まで沈み込まないかを確認します。
- エンジンを始動し、再度ペダルタッチを確認します。
- 車をゆっくりと動かし、周囲に注意しながら低速でブレーキの効き具合を試運転で確認します。異常があればすぐに停車し、原因を究明してください。
- 数日間はフルード漏れがないか、リザーバータンクのレベルが変化していないかなどを定期的にチェックすることをお勧めします。
これらの注意点を厳守し、安全第一で作業を進めることが、ブレーキフルード交換を成功させる鍵となります。少しでも不安や疑問がある場合は、無理をせずプロの整備士に相談しましょう。
6. 車のブレーキフルード交換 完全ガイドのコツ
ブレーキフルード交換作業をスムーズかつ確実に進めるためには、いくつかの「コツ」を知っておくと非常に役立ちます。これらのヒントを活用することで、作業の効率が向上し、より安全な結果に繋がるでしょう。
- 一人でのエア抜きを効率化するコツ:
- ワンウェイバルブ付きブリーダーキット: 市販されているワンウェイバルブ(逆流防止弁)付きのホースや専用ツールを使用すると、一人でもエア抜きが格段に楽になります。ペダルを踏み、バルブを緩めるとフルードが排出され、ペダルを離しても空気が逆流しないため、ブリーダーバルブを毎回締めたり緩めたりする手間が省けます。
- 真空ポンプ式フルードブリーダー: ブリーダーバルブからフルードを吸い出すことで、一人で簡単にエア抜きができます。ただし、リザーバータンクのフルードレベルが下がりすぎないように注意が必要です。
- 効率的な作業順序の選択:
- 一般的にはマスターシリンダーから最も遠い車輪から順に作業しますが、一部の車種では異なる順序が推奨される場合があります。必ず車の取扱説明書や整備マニュアルを確認してください。
- 作業を中断する際は、必ずリザーバータンクのフルードレベルをMIN以上にしておき、エア噛みを防ぎましょう。
- 新旧フルードの色差を利用する:
- 新しいブレーキフルードは通常、透明か薄い黄色をしています。古いフルードは劣化により茶色や黒っぽい色に変色していることが多いです。
- ブリーダーバルブから排出されるフルードの色が、古い色から新しいフルードの色に完全に変わるまで排出を続けることで、フルードの交換が完了した目安とすることができます。排出ホースが透明であると、この色の変化を視覚的に確認しやすくなります。
- ブリーダーバルブの固着対策:
- 固着しやすいブリーダーバルブには、作業前に浸透潤滑剤(例: WD-40など)を塗布し、数分から数十分放置してから作業を開始すると、固着が解消されやすくなります。
- 固着がひどい場合は、無理に力を加えず、バーナーで軽く炙って熱膨張を利用する方法もありますが、これは専門知識と経験が必要なため、自信がない場合はプロに依頼しましょう。
- マスターシリンダーの液面を常に監視する習慣:
- エア抜き作業中は、常にリザーバータンクのフルードレベルに注意を払いましょう。少しでも液面が下がったらすぐに補充する習慣をつけることで、エア噛みのリスクを大幅に減らせます。近くに新しいフルードをスタンバイさせておくのが良いでしょう。
- ブレーキクリーナーの活用:
- フルードが飛び散った際や、作業後の清掃にはブレーキクリーナーが非常に有効です。油分を素早く分解し、残渣を残しにくい性質があります。ただし、ゴム部品には影響を与える可能性があるので、使用箇所には注意が必要です。
これらのコツを実践することで、ブレーキフルード交換作業の難易度が下がり、より安全で確実なメンテナンスが可能になります。
7. 車のブレーキフルード交換 完全ガイドの応用アイデア
ブレーキフルードの交換は単なる定期メンテナンスに留まらず、車のパフォーマンス向上や他のメンテナンス作業と組み合わせることで、さらにその価値を高めることができます。ここでは、ブレーキフルード交換を応用するいくつかのアイデアをご紹介します。
- スポーツ走行やサーキット走行を考慮したフルード選び:
- 一般道での走行がメインであればDOT3やDOT4で十分ですが、スポーツ走行やサーキット走行を行う場合は、より高い耐熱性を持つDOT4やDOT5.1のような高沸点フルードへの交換を検討しましょう。これらのフルードは、過酷なブレーキング条件下でもベーパーロック現象の発生リスクを低減し、安定したブレーキ性能を維持します。
- ただし、高沸点フルードは吸湿性も高い傾向にあるため、通常のフルードよりも短い間隔での交換が必要になる場合があります。
- ブレーキホースの同時交換(ステンメッシュホース化):
- ブレーキフルード交換の際に、純正のゴム製ブレーキホースをステンレスメッシュ製のブレーキホースに交換するのも良いアイデアです。ゴム製ホースは加圧時に膨張するため、ブレーキペダルの踏み込み量が大きくなりがちですが、ステンメッシュホースは膨張が少ないため、よりダイレクトでカッチリとしたペダルタッチを実現し、ブレーキの応答性を向上させます。
- フルード交換と同時に行えば、二度手間にならず効率的です。
- ブレーキキャリパーのオーバーホールと同時作業:
- 走行距離が伸びた車や、ブレーキの引きずり、片効きなどの症状が見られる場合は、ブレーキフルード交換のタイミングでブレーキキャリパーのオーバーホール(分解清掃、ピストンシールやダストブーツの交換)を行うことを検討しましょう。
- キャリパー内部のピストンやシールの劣化は、ブレーキ性能の低下や固着の原因となります。オーバーホールとフルード交換を同時に行うことで、ブレーキシステム全体の性能を新車に近い状態に回復させることができます。
- クラッチフルードの交換(多くの場合、ブレーキフルードと共用):
- マニュアルトランスミッション車の場合、クラッチの油圧システムにもブレーキフルードが使用されていることがほとんどです。クラッチフルードもブレーキフルードと同様に吸湿し劣化するため、ブレーキフルード交換時にクラッチフルードも同時に交換することで、クラッチペダルのタッチ改善やシステムの長寿命化に繋がります。
- クラッチフルードのリザーバータンクは、ブレーキフルードのリザーバータンクと一体になっている場合や、別の場所に独立して設置されている場合があります。
- 劣化したフルードが引き起こす可能性のあるトラブルの予兆:
- ブレーキフルードの劣化は、ブレーキペダルのフワフワ感、ブレーキの効き始めが遅い、ブレーキが鳴くなどの症状として現れることがあります。これらの予兆を早期に察知し、フルード交換や点検を行うことで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
これらの応用アイデアは、単なるメンテナンスを超えて、愛車のブレーキシステムをより安全で高性能なものにするための投資とも言えます。
8. 車のブレーキフルード交換 完全ガイドの予算と費用
ブレーキフルードの交換にかかる費用は、DIYで行うか、プロに依頼するかによって大きく異なります。それぞれのケースでどのような費用が発生するのかを詳しく見ていきましょう。
1. DIYの場合の費用
DIYでブレーキフルードを交換する場合、主な費用は材料費と工具代です。
- ブレーキフルード代:
- DOT3、DOT4であれば、1Lあたり1,000円~3,000円程度が目安です。高性能なDOT5.1になると、3,000円~5,000円程度になることもあります。一般的に、乗用車1台分の交換には1L~2L程度あれば十分です。
- 工具代:
- ジャッキ、リジットラック、メガネレンチ、透明ホース、廃油受け、トルクレンチなどは、すでに持っているものがあれば費用はかかりません。持っていない場合は、一式揃えるのに5,000円~20,000円程度かかることがあります。特にトルクレンチは安全に関わるため、安価なものでも用意することをお勧めします。
- 一人での作業を効率化するワンウェイバルブ付きブリーダーキットや真空ポンプは、2,000円~10,000円程度で購入できます。
- 廃油処理費用:
- 廃油処理箱は数百円で購入できます。ガソリンスタンドや整備工場での引き取りには、別途費用がかかる場合があります。
DIYの最大のメリットは工賃がかからないため、材料費と工具代のみで済む点です。初期投資として工具代がかかりますが、一度揃えれば繰り返し使用できるため、長期的に見ればコストパフォーマンスは高いと言えます。ただし、 ⚠️ DIYには作業ミスによるリスクが伴います。ブレーキは安全に直結する部品であるため、確実な作業が求められます。この費用は「安全に対する投資」であり、決して惜しむべきではありません。
2. プロに依頼する場合の費用
ディーラー、カー用品店、一般整備工場など、依頼する場所によって費用は異なりますが、一般的に工賃と材料費が含まれます。
- 工賃:
- ブレーキフルード交換の工賃は、4,000円~10,000円程度が一般的です。車種や依頼する店舗によって変動します。
- ブレーキフルード代(材料費):
- 店舗が用意するフルードを使用する場合、フルード代は別途請求されます。一般的にDIYで購入するよりも少し割高になる傾向がありますが、品質の保証されたフルードが使用されます。
- 合計費用:
- トータルで5,000円~15,000円程度が目安となるでしょう。
依頼先ごとの特徴:
- ディーラー: 純正フルードを使用し、車種に精通した整備士が作業するため、最も安心感があります。費用は高めになる傾向があります。
- カー用品店: 比較的リーズナブルな価格設定が多く、手軽に依頼できます。ただし、整備士の技術レベルは店舗によって差がある場合があります。
- 一般整備工場: 費用はディーラーとカー用品店の中間くらいで、長年の経験を持つ熟練の整備士がいることが多く、きめ細やかな対応が期待できます。
費用を抑えたい場合はDIYも選択肢ですが、ブレーキシステムのメンテナンスはプロに任せるのが最も安心で確実な方法です。特に、作業に少しでも不安がある場合は、無理をせずプロに依頼する費用を「安全への投資」と捉えるべきでしょう。
まとめ:車のブレーキフルード交換 完全ガイドを成功させるために
車のブレーキフルード交換は、単なるオイル交換とは異なり、ドライバーと同乗者の命を守るための極めて重要なメンテナンス作業です。この完全ガイドを通じて、ブレーキフルードの基本から種類、交換手順、注意点、そして応用アイデアや費用まで、幅広い知識を習得いただけたことと思います。
ブレーキフルードは吸湿性という特性上、時間とともに確実に劣化し、その性能が低下します。劣化したフルードを使い続けることは、ブレーキの効きが悪くなる「ベーパーロック現象」を引き起こす可能性があり、重大な事故に直結する危険性をはらんでいます。そのため、定期的な交換が何よりも重要です。
DIYでの交換はコストを抑え、愛車への理解を深める良い機会となりますが、同時に確かな知識、適切な工具、そして細心の注意が求められます。特に、エア噛みを防ぎ、ブリーダーバルブの締め付けトルクを管理するなど、一つ一つの工程を確実に実行することが成功の鍵です。少しでも不安を感じる場合は、迷わずプロの整備士に依頼することをお勧めします。プロの技術と経験は、何物にも代えがたい安心を提供してくれます。
最終的に、ブレーキフルード交換を成功させるために最も大切なことは、「安全第一」の原則です。愛車の安全な走行性能を維持し、快適なカーライフを送るためにも、このガイドで得た知識を活かし、適切なタイミングでブレーキフルードの交換を行いましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
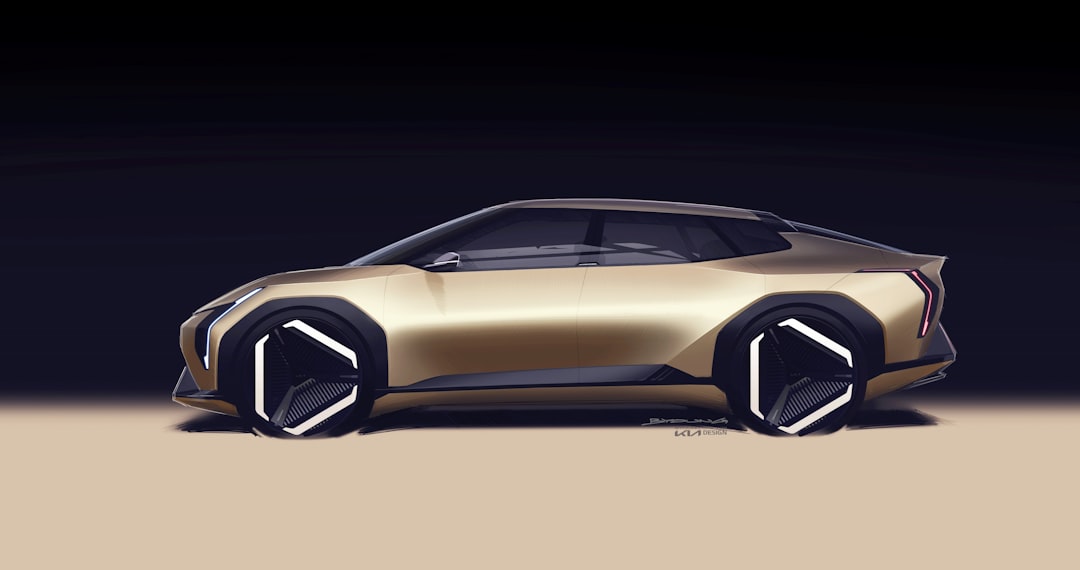
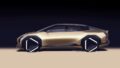
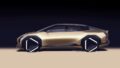
コメント